№23 滝子山夏山行、大月市の秀麗富嶽十二景の <p1>
6月 5日[木](晴れ) 初狩から笹子へ
 |
 |
| (初狩藤沢集落から滝子山) | (滝子山からの富士・大月市富嶽十二景) |
交通費(324+1116+640+760+1166+324=\4330) <歩行約7時間半>
 少し早めに出発して小田急藤沢駅急行上り一番電車に。町田で乗り換え、横浜線では地図広げて行き先検討。取り敢えず八王子から中央線始発の松本行きに乗って大月辺りでどこの山にするか車窓見ながら決定と。天気良さそうなので塩山まで乗って大菩薩峠もあるかなと思いながら。横浜線からの車窓で西は快晴、空気の澄んでいたので大菩薩にしようかと思いながら八王子始発の松本行きに乗った。 (滝子山地図 →)
少し早めに出発して小田急藤沢駅急行上り一番電車に。町田で乗り換え、横浜線では地図広げて行き先検討。取り敢えず八王子から中央線始発の松本行きに乗って大月辺りでどこの山にするか車窓見ながら決定と。天気良さそうなので塩山まで乗って大菩薩峠もあるかなと思いながら。横浜線からの車窓で西は快晴、空気の澄んでいたので大菩薩にしようかと思いながら八王子始発の松本行きに乗った。 (滝子山地図 →)
横長の椅子席、向かって左側の見える方に座った。車両は空いて山格好の人もそれなり。その年輩ハイカーが背中の日除けを降ろしてしまったのに少々がっかり。車窓など見ず寝込むような人だった、他はそのままで景色は見られたが写真は撮れず。大月辺りで最終決定と思っていたが、上野原辺りから山がよく見えていたので扇山も良いかなと思うもそのまま、それに大月で富士急線に乗り換え杓子山か三ツ峠でもいいかなと、でもそのまま。
 |
 |
| (初狩駅到着7:30) | (初狩駅付近、富士のぞく) |
大月で滝子山がすっきり見えたのには初狩駅でぱっと降りた。後の祭りだが富士がよく見えて大菩薩山稜もすっきりだったので大菩薩峠にすればとは遅し。二人が山に向かっていた。国道20号線出る前に富士もちらっと見えて、鶴ヶ鳥屋山には新しき送電鉄塔も出来ていた。
 |
 |
| (初狩から滝子山望む) | (同じく鶴ヶ鳥屋山) |
橋を渡って中央道くぐっていけば藤沢の集落、通学時間帯だがもう子供らの姿を見ることはない。時折車が行き交うばかり。振り返ってみる富士は雪が溶けてはいるが秀麗。送電鉄塔に興味があるのでその富士とコラボして撮るのも楽しみだった。こちらは66KVだが、あの滝子山の右尾根筋を越えていくのは500KVの葛野川線だ。あの碍子の多さも絵になるが少々遠い。
(送電線が滝子山の裾沿いに →) (東電笛駒線鉄塔 95) (JR大月-勝沼線鉄塔32 →) |
 |
 |
 |
 |
| (藤沢集落から鶴ヶ鳥屋山) | (同じく、300ミリ望遠で富士山) |
集落に少しある田んぼは若苗がそよいでいた。周りの山間の緑も濃くなっている。村の突き当たりに藤沢子神社、樹齢6百年とかの大杉が迎えてくれた。石灯籠があるが狛犬がいないのは寂しき。拝殿に拝礼してしばし厳かなる雰囲気に佇む。鳥居の先に富士も見えて、人影まったく無いのも良し。山への気分を上げていく。
 |
 |
| (藤沢集落から送電鉄塔) | (藤沢集落田植えの頃) |
 |
 |
| (玄関先に熊の彫り物が) | (藤沢集落から富士見ゆ) |
 |
 |
| (望遠で富士山を) | (藤沢子神社の鳥居) |
 |
(← 子神社社殿) . (子神社の神木・大杉) (← 子神社から富士が) . |
 |
神社裏手の殿山への標識があったが不案内なのでそのまま予定通り滝子山登山口へ。傍らを流れる藤沢に大水が出たか、その工事の事務所があり新コンクリートの砂防ダムも見えた。見覚えのある登山口を左手に登っていけば2軒の家があるがもう朽ちていくだけ。その屋根の上は空いて富士が見えるのは毎回楽しみでもある。そこから植林の薄暗い山道となる。
 |
 |
| (藤沢集落最奥の家) | (そのもう1軒に富士のぞく) |
ウグイスなどが鳴くばかりの静かな道、と、後から熊鈴の音、振り返れば犬連れの年輩者だった。そのまま見送って後から。でも沢に出合う辺りで引き返してきた。飼い犬は少し唸り、飼い主が首を引っ張って抑えてたので何事もなし。朝の散歩だったか、その先は沢沿い、ミソサザイを期待したが生憎、その沢音には気分よく登っていく。
 |
(← 檜林を登ってゆく) . (小沢の小滝) (← 細き小沢の仮桟敷きを) . |
 |
 |
 |
 |
| (犬連れて散策) | (丸太橋を渡って) | (恩賜林へ) |
 |
 |
 |
| (半世紀前の植林) | (その桧育って) | (林床にはフタリシズカが) |
沢を横切ったり小滝を見たりして見覚えのある恩賜林の看板に。狭くなった峡谷のような道を抜ければ急な植林地帯。昭和47年植林と半世紀経っているので桧も随分伸びていた。見上げるような道を一踏ん張りすれば最後の水場だった。
 |
 |
| (トチノキの若葉) | (最後の水場のベンチで) |
 |
 |
 |
| (檜大木) | (ケヤキ大木) | (老大木) |
ベンチがあるので毎度ここで休憩、汗を拭く。あの犬散歩の人以外に人影はなかった。大木が1本、ここの主のように。お茶菓子食べテルモスのお湯を飲んでひと息つく。水場の小屋は見ただけで登って行く。見覚えのある大木が幾つか、それを見上げたり撮ったりして急斜面を頑張る。ロープ伝いに尾根へ上がってもまだ峠は先だった。
 |
 |
| (手入れされず密集の植林) | (抜けて雑木の乗越分岐) |
 |
 |
 |
| (乗越で休憩) | (木立越しに富士見えるも) | (ヤマツツジ愛でながら) |
ようようになだらかになって標識が見えた。初狩駅からもう一つのコースだが利用したことなし。雑木尾根で展望は良くないのでひと息入れただけで滝子山へ向かう。ツツジが林間に咲いていたがそう目立たず。すっかり緑濃くなった雑木尾根で展望は利かず。 何とか富士が見えたがもちろん写真にならずでストレスはたまる。何度も歩いている道で檜平まで行けば富士がすっきり見えると結構な尾根道を辿った。
何とか富士が見えたがもちろん写真にならずでストレスはたまる。何度も歩いている道で檜平まで行けば富士がすっきり見えると結構な尾根道を辿った。
(檜平 →)
途中からハルセミの鳴き声が聞こえてきたので録音器も取り出した。暑いが風があり涼しいくらい、蝉の録音しながらひと息つき気分も良くなった。ヒガラなども鳴いて、その聞きなしはツルベッ、ツルベッ、朗らかに。それでも檜平までは結構時間が。
 |
 |
| (檜平からツツジと富士山を) | |
ようように看板が見えて檜平に、思ったよりスッキリしてない広場だったが富士を撮るには悪くなし。でも雪がだいぶ溶けてきた富士は幾分霞んで雲も湧いていた。前景にツツジを入れて300㍉望遠に換えたりしながらしばし写真を。風があり蝉時雨の録音は今一つも、まだ誰とも会わずや静かで良し。
疲れていたが男坂を登っていく。見上げるような登りも何とか、男女坂合流点過ぎて登った岩ごつごつの斜面で危うくザックに引っ張られる形で後ろ向きに倒れ込むようなことも。そんなこんなでバテて座りこんで一休みも.見上げれば若葉が輝きツツジも咲いていた。
 |
 |
 |
| (フタリシズカ) | (三人組と) | (ヤマツツジ) |
 |
 |
| (三角点ある滝子山は展望なし) | (大谷ヶ丸分岐過ぎて山頂へ) |
元気を取り戻し登っていけば賑やかな人声が、男性に女性二人の組がわいわい降りて来た。挨拶交わしただけで見送る。その先幾分なだらかな尾根になったところでも男性一人を見た。やはり滝子山は人気だ。笹子駅から登って来る人が多い。滝子山の三角点見て直ぐすみ沢へ下る分岐。ここからひと登りでようやくスッキリした展望のある滝子山山頂だった。
 |
 |
| (滝子山山頂に 12:15) | (大月市秀麗富嶽十二景の滝子山富士) |
 |
 |
| (ツツジも咲く山頂) | (乾杯と) |
. (富士に乾杯 →) (滝子山山頂で小宴昼餉、 . 12:15~13:20 ↑→) |
 |
 |
先客はおばさんと若者二人が、挨拶交わし取り敢えず富士を撮る。ツツジが咲き誇っていたのも良し。富士山にまだ雲が湧いていなかったのも運が良かった。身延近くからやって来たという初老婦人としばらく話し込む。あれが三ツ峠というとびっくりしていた。地元のようだがまだ山登りは最近始めたばかりとか、それでもこの滝子山へ登ってきていたのには感心、こちらを見て若いからとか言われたので一応幾つくらいですかと聞けば70はとうに過ぎているようなことを。まさか80にはなってないだろうとその元気さに。地図をよく見ていて初狩には2~3時間で下れますかねと。
しばらくしてこちらもシートを敷いて缶ビール一杯だった。若者はちょろちょろしていたがは口をきくことはなかった。去ってから代わりにインド人かスリランカのような真っ黒の顔した若い外人がやって来た。こちらとも口をきくことなし。おばさんはその内下って行ったがどっちへ下ったか知らず。
 |
 |
| (山頂で若者とおばさん) | (顔黒き若者が、インドかスリランカ?) |
 |
 |
| (都留市方面展望) | (黒岳に雁ヶ腹摺山展望) |
 |
(← 滝子山地図) |
また替わりに賑やかな若い女性二人が登ってきた。その二人に途中で人に会いましたかと聞けば女性に会いましたとすみ沢方面のコースでと。年輩の女性でしたかと聞けば若い小柄な人だったとは違ったかなと思うも、さっきのおばさんくらいしか女性はいなかったがと思いながら片付ける。
 |
(← いつの間にか迷い込んで) (稜線尾根へ目印の高木) (← 沢へ行き詰まって戻る) . |
 |
分岐まで戻り下って行ったが直ぐ祠のある鎮西ヶ池だったが通り過ぎたのかそのまま下って沢にぶつかる辺りでおかしいと、その先は道らしきものがなく狭い沢に落ちていくばかり。
途中で標識もなく標しもないのでおかしいと思っていたが、このまま下ると危ない目に遭うと右手の唐松の植林へ上がっていく。ヤブではないので歩くには苦労しなかったがそれでも登り返しはきつし。
(← 防火帯尾根)
右へ行けば大谷ヶ丸の尾根から下るコースにぶつかると見当つけて行けば見覚えのある広い防火帯の尾根道に出た。1本道の下りで祠のある鎮西の池広場に出るはずだったか、何だかきつねに化かされたようにそのまま左に入込み下ったようだ。それを確かめようとは思わずそのままコースを下っていく。
 |
(← 山梨の森100選の美林へ) (←↑ その美しき森へ下る) |
 |
広い尾根道でもう間違うことなくすみ沢へ。山梨の森100選の看板が、右へ登って行けば大谷ヶ丸だ。左へ下って行く。沢が出てきて迷ったところでも見た花が群れ咲いていた。クリンソウか、汗をかいていたので沢水で汗を拭きたかったがもう少し下ってからと行けば難路の沢の分岐に出た。迷わず沢沿いと難路へ突っ込んでいく。
 |
 |
| (沢にぶつかればクリンソウが) | (すみ沢上部の滝) |
 |
 |
 |
|
| (クリンソウ) | (沢沿いの難路へ) | (20分後に迂回路と合流) | |
 |
 |
 |
|
| (モチガ滝?) | (すみ沢) | (三丈の滝) |
. (すみ沢の小滝 →) (ブナの木) . (木橋を渡って →) |
 |
 |
後悔先に立たず、幾つかの滝を見られたが砂のような斜面など足元のおぼつかない不安定な道には気を使った。ミソサザイの囀りが聞こえてきたが録音どころではなし。滝の写真はなんとか撮っていく。前は何々の滝と確かめる余裕があったがもう目が悪くなって橫目で見るだけのような。それでもシャッター速度変えたりしながら滝を撮っていく。20分ほど下って迂回路と合流は意外と短し。すぐ老年輩の二人が休んでいるのに出合った。挨拶しただけで先へ下る。木橋が出てきて渡ったところで振り向けば二人はそのままついてきていた。
. (東電 笛駒線鉄塔77 →) (根っこに巣くって幾星霜) (笛駒線鉄塔66KV・77の結界 →) |
 |
 |
 |
 |
 |
| (笛駒線鉄塔の名盤) | (老年輩二人が) | (道証地蔵登山口) |
もう気楽と思ったが中々、結構長かった。沢から離れて樹林帯の歩きやすい道となったがさすがに疲れが。好きな送電鉄塔が森の中に見えたが少し離れていたので撮りに行く余裕なし。でもその下った先にもう一つあった。こちらは道脇ザックを降ろし休憩がてら鉄塔の結界などを撮る。案内標識はなかったが鉄塔に名盤はあった。東京電力笛駒線77と。先程の二人が横を下っていくのを見送った。水を飲み飴をかじって幾分回復してザックを担いだ。歩きやすくなった下り道だったがそれでもまだ結構下った。
送電鉄塔はもう一つあったがやはり見に行くには少々離れていたので番号の順番はしれず。ようように登山口が見えてきて林道に出た。カウンターを押して見覚えのある地蔵さんに拝礼
道証地蔵登山口だった。駅までもう辿るだけだったが、また駅まで長いのは覚悟した。
 |
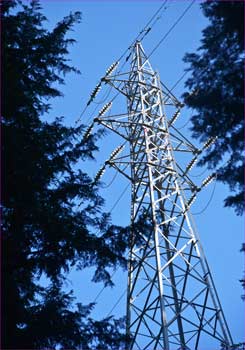 |
 |
| (道証地蔵) | (笛駒線鉄塔) | (田通乃姥神) |
先程の二人は車だったようで道脇の車の傍で帰りの支度していた。うまく行けば乗せてくれるかなとちょこっと思いながら先へ急ぐ。左に田通乃姥神なんてのも覚えはあったが案内なしで見ただけ。17時前の電車は無理かなと思いながら林道を急ぐ。
 |
 |
| (笛駒線鉄塔が) | (中央道陸橋、鶴ヶ鳥屋山見ゆ) |
 |
 |
| (陸橋から振り返って) | (鶴ヶ鳥屋山と葛野川線送電鉄塔) |
 笹子の向かいの山稜が見えてくればほっとする。回り込むようにして下れば通行止めフェンスが、簡単に開けられて抜ければ車が駐車してあった。南稜へ行く道は気づかず。抜けていけば中央道の陸橋、向かいに送電鉄塔立つ鶴ヶ鳥屋山がすっきり見えて半月が中天にあった。
笹子の向かいの山稜が見えてくればほっとする。回り込むようにして下れば通行止めフェンスが、簡単に開けられて抜ければ車が駐車してあった。南稜へ行く道は気づかず。抜けていけば中央道の陸橋、向かいに送電鉄塔立つ鶴ヶ鳥屋山がすっきり見えて半月が中天にあった。
標識通りに下れば神村神社、一応拝観と裏から境内へ。拝殿は特に見る物無しも屋根に囲われた本殿はりっぱ。境内には遊び場があり三本幹の杉神木もあった。狛犬はなかったが石灯籠は2対が。
. (稲村神社本殿 →) (稲村神社の神木・三本幹杉) . (笹子の稲村神社 →) |
 |
 |
靖国鳥居をくぐり石段降りて通りへだったが、さて笹子駅へはどっちだったかと、案内なくスマホでマップを見たら右へだった。確か前回は道を聞いた人に車で送ってもらった記憶があった。周りに家はあったが人影見えず。そこへ電車の音が、あずさ号が走り去るのを見送るだけ。
 |
 |
| (吉久保であずさ号が) | (バス車窓から葛野川線鉄塔) |
国道にでて笹子駅へ向かおうと行けばバスが見えた。国道からこっちの集落へ入ってきたので手を振ったら停まってくれた。若い女運転手だった。助かりましたとお礼言いながらその大月駅行きバスに乗り込んだ。誰も乗っていなかった。取り敢えず駅まで歩かなくて済んだ。初狩駅で降りることも考えず終点大月まで。大月からは特急でと思いながら。所々寄り道しながらのどかに。大月の病院まで貸し切りだった。
大月駅に17時半前に着いて時刻表見れば、東京行き快速が直ぐあったが、特急は17時45分がありそっちに。でも切符売り場には異邦人の列が、駅員に聞けばホームでも購入出来ますよと。それでスイカで入って売店で缶ビール買いこんでホームへ。販売機は二人目くらいで空いたが夕日が差し込むようなところで画面がはっきり見えず目が悪いので進まず。後にいた若い女性に助け船で何とか特急券は買えたが指定席は満席だった。
 |
 |
| (JR大月駅前) | (特急あずさ号に 17:42) |
富士急線から入って来ていた特急は前の方、松本から来る特急あずさ号接続だったので席が空いてるかもと期待して後から来た特急に乗り込んだが生憎。最後尾の荷物置き場の横で缶ビール立ち飲みとなった。デッキの方も満杯になっていた。やはり外人さんも多し。車窓もよく見えないので缶ビール飲むだけ、つまみも不自由だった。車掌が来たが特急券は購入していたので問題なし。次は八王子と我慢してビールを空けた。八王子近くなって早々に降りようとして来た年輩の女性に、まだ早いですよと言いながらしばし世間話を。荷があったので早めにと言いながら八王子までつきあってくれた。
八王子駅では直ぐ横浜線へ、待っていた電車は混んでいたが次のはまだで、10分以上待つのにはそのまま乗り込んで町田まで立ちっぱなし。いつも思うが八王子から町田まで空くことなしである。町田でもそのまま来た電車に乗りこめば相模大野で始発の藤沢行きがあり座れたのでほっと。暗くなった藤沢に19時半に帰着だった。
<先頭ページへ> (山辰通信6/7)
※送電線鉄塔記録……東電笛駒線鉄塔77、95。JR大月勝沼線鉄塔32、葛野川線鉄塔を幾つか。
※藤沢の子神社、笹子の稲村神社。
※ニコンデジカメD750、ズーム24~120㍉、70~300㍉。キャノンG7X使用。
(令和7年6月11日記録完)