№26 白馬三山夏の旅 幕営2泊3日 (7/21~7/23)
7月21日[火](晴曇り) 白馬鑓温泉へ <p1>
テント代1000円入湯代500円 缶ビール350*3=1800円 往路交通費(4750+4200+1800+1000=\11750)
 |
 |
| (7/22 鑓温泉展望) | (7/22 鑓ヶ岳山頂) |
 東京に6時前、まだ余裕が有り改札入らず待合椅子でしばし休む。かがやきにも慣れてビール買い込んで。2連席の窓側、出発して地下を抜け上野を過ぎた辺りで旅立ちの祝いに缶ビールを開けた。
雲が多いながらも天気はまずまず。高崎を抜け軽井沢過ぎると長野は近し。
東京に6時前、まだ余裕が有り改札入らず待合椅子でしばし休む。かがやきにも慣れてビール買い込んで。2連席の窓側、出発して地下を抜け上野を過ぎた辺りで旅立ちの祝いに缶ビールを開けた。
雲が多いながらも天気はまずまず。高崎を抜け軽井沢過ぎると長野は近し。
4月唐松岳以来の長野駅、東口バス発着所や切符の購入も迷うことなし。夏休みに入って客は多しもまだ余裕があった。扇沢行きも山客が多し。後ろに並んでいた年配の4人組に切符の購入場所を教えたら、 回数券で購入して一人1800円のところ1400円とは安し。買った後だったのでもう遅し。その4人組は栂池公園まで。
 もう日は高く暑し。バスは旅行客もいたがまだ空いていた。後から乗った若い外人二人連れは別々の席に、その白人女性と同席となった男性が会話しているのが聞こえたが女性の発音は耳に心地良し。
見慣れた車窓もぼんやり眺めているだけで気分は乗って行く。山を越えて前方に鹿島槍ヶ岳などが見えれば糸魚川街道は近い。白馬駅に時間通り到着。
もう日は高く暑し。バスは旅行客もいたがまだ空いていた。後から乗った若い外人二人連れは別々の席に、その白人女性と同席となった男性が会話しているのが聞こえたが女性の発音は耳に心地良し。
見慣れた車窓もぼんやり眺めているだけで気分は乗って行く。山を越えて前方に鹿島槍ヶ岳などが見えれば糸魚川街道は近い。白馬駅に時間通り到着。
猿倉行き乗り換えに30分ほどあった。何組か同じような登山者が並んでいた。その中の3人組がタクシーでもと声をかけてきたが運ちゃんが来たら待っててとトイレに買い物を済ます。 戻ってみると交渉には来なかったようでもうバスを待っても変わらない時間に。その3人組は同じように鑓温泉へ。白馬岳から祖母谷温泉へ下ってトロッコで宇奈月へ出ると羨ましい計画だった。 栂池新道も歩いたとか、山慣れしている年配者たち。
 幾分か古いバスに乗り込み猿倉へ。八方のバスセンターから乗った連中も長野から同じの。そのまま何度も通った猿倉への森へと入って行く。まだ下ってくる車は少なかった。猿倉に10時、
昼に食べられそうなのを山荘に聞いたが生憎。結構な年配の団体さんとも合流で賑やかな歩きはじめだった。3人組はさっさと登ってそれっきり合うことはなく、祖母谷の泊まりやトロッコ列車のことを聞きたかったのだったが。
幾分か古いバスに乗り込み猿倉へ。八方のバスセンターから乗った連中も長野から同じの。そのまま何度も通った猿倉への森へと入って行く。まだ下ってくる車は少なかった。猿倉に10時、
昼に食べられそうなのを山荘に聞いたが生憎。結構な年配の団体さんとも合流で賑やかな歩きはじめだった。3人組はさっさと登ってそれっきり合うことはなく、祖母谷の泊まりやトロッコ列車のことを聞きたかったのだったが。
林道に出て直ぐ白馬尻への道を左のブナ林に入って行く。鬱蒼としたブナの森も暑さはこたえた。後ろから追いつかれると直ぐ道を譲る。前からも丁度鑓温泉から下ってくる時間でよく擦れちがった。 ガチャガチャ鳴り物が教えてくれる。蝉の声が森の奥から聞こえメボソムシクイなどの囀りもと気分は乗って行く。一汗かいてブナ林途中で一休憩。
 背の高い男性にぽっちゃり形の女性の二人連れが登ってきて先へ行くも、しばらく追いつ追われつだった。ブナの森を抜けても雑木林が続き、背は低いが展望はなかなか利かなかった。
幾分急な道になったところで背後の展望が開けた。白馬岳の山稜が見えたがいつの間にか雲に覆われていた。それでも雪渓も見え稜線も遙かにでまずまず。狭い上り道の幾分広くなったところ、
往来する登山者に迷惑のようもそこへザック降ろし休憩。
背の高い男性にぽっちゃり形の女性の二人連れが登ってきて先へ行くも、しばらく追いつ追われつだった。ブナの森を抜けても雑木林が続き、背は低いが展望はなかなか利かなかった。
幾分急な道になったところで背後の展望が開けた。白馬岳の山稜が見えたがいつの間にか雲に覆われていた。それでも雪渓も見え稜線も遙かにでまずまず。狭い上り道の幾分広くなったところ、
往来する登山者に迷惑のようもそこへザック降ろし休憩。
缶ビール出して山始めの乾杯、定番のサラダに枝豆つまみながら。もちろんお湯など湧かせる場所ではなく窮屈だった。先程の二人連れも追いついてきてやっと展望が利きましたのでと挨拶がてら。
その二人も直ぐ上で休んでいた。一頻り下って行く人も途絶えて静かになってまた登りだす。
二人にお先にと登って行けば林を抜け広々と展望の利くトラバース道に出た。東は晴れて高妻山などが見えた。下って来た女性が防虫網を被っていたのでアブはすごいですかと挨拶がてらに。そんなでもない返事だったが目の周りに小虫がたかっていた。
高山植物も道沿いに黄色い花など展開するようになって気分が晴れて行く。上空は雲が広がっていた。
沢にぶつかったところでザックを下ろしまた汗を拭く。喉も潤した。 もう少しのぼって行けばニッコウキスゲも咲き、コバイケイソウもちらほら、小さな湿原地帯に。
もう少しのぼって行けばニッコウキスゲも咲き、コバイケイソウもちらほら、小さな湿原地帯に。
気分良くなって一登り、見覚えのある岳樺の木、小日向のコルに。 藪に覆われているが冬時分はここから杓子岳を目指すのだ 。いつかはと思ってもまだ実現はしていない。すぐ脇に小さな池、水芭蕉が大きく葉を広げていた。
。いつかはと思ってもまだ実現はしていない。すぐ脇に小さな池、水芭蕉が大きく葉を広げていた。
 ちょいとした湿地帯がしばらく。キヌガサソウなどが目をひいて、蛙の合唱も聞こえ来る。その先の左手に小さな池。湿地とも判然としない沼原を水芭蕉の白い花が咲き群れていたのは嬉しき。
ウグイスも長閑に囀っていた。周りは藪で展望は利かなかったが心安まる別天地だった。
ちょいとした湿地帯がしばらく。キヌガサソウなどが目をひいて、蛙の合唱も聞こえ来る。その先の左手に小さな池。湿地とも判然としない沼原を水芭蕉の白い花が咲き群れていたのは嬉しき。
ウグイスも長閑に囀っていた。周りは藪で展望は利かなかったが心安まる別天地だった。
そこをくぐり抜ければ前方が一気に開けた。 雄大な山脈、雪渓も未だ豊富な斜面が。
その一角に今宵の泊まり場である鑓温泉の建物が見えた。まだ遙かであった。
雄大な山脈、雪渓も未だ豊富な斜面が。
その一角に今宵の泊まり場である鑓温泉の建物が見えた。まだ遙かであった。
下って草原に雪渓幾つか、沢音も聞こえて気持ち良いところぶらり。右手の白馬山稜は厚い雲に覆われていたが左手八方尾根辺りから安曇野側は青空が見えていた。浮き雲も地平に幾つも浮いている。
蛙の声やウグイスなどの囀りに録音をとザックを降ろそうとしたところで首にぶら下げていたカメラが落っこちた。 ストラップが切れたのだ。まだ買ってそう経っていないと全然気にしていなかったのだ。
その応急処置にしばらくかかった。数人のグループがその間に降りて来た。白馬からの連中か挨拶交わしただけ。蛙の声もその間止んでいた。(八方尾根望む→)
ストラップが切れたのだ。まだ買ってそう経っていないと全然気にしていなかったのだ。
その応急処置にしばらくかかった。数人のグループがその間に降りて来た。白馬からの連中か挨拶交わしただけ。蛙の声もその間止んでいた。(八方尾根望む→)
今度は雨が落ちてきた。あーと思ったが直ぐ止んでカッパを出すまでもなく助かった。肩にかけられるようにストラップの手結び処置が出来た。また重き荷を背負って行く。直ぐ広々とした雪渓に出て気分がほころんだ。 ここで一休みして支稜を越える鋭気を養う。右から流れ落ちてくる雪解け水は豊かな勢いだった。中天の雲間に三日月が浮かぶ。
 登っていけば若い単独行者と出合う。鑓温泉までの時間を聞けば早くて一時間はと、また気を引き締める。支稜越えれば同じく山稜中腹に鑓温泉が見えたがやはりまだまだ。
難儀な杓子沢トラバースにその名も落石沢などを辿って行かねばならなかった。このコースではいつも山稜が雲に閉ざされている。
登っていけば若い単独行者と出合う。鑓温泉までの時間を聞けば早くて一時間はと、また気を引き締める。支稜越えれば同じく山稜中腹に鑓温泉が見えたがやはりまだまだ。
難儀な杓子沢トラバースにその名も落石沢などを辿って行かねばならなかった。このコースではいつも山稜が雲に閉ざされている。 遙かな山巓は杓子に鑓が天を突いているはずだが。今にも雨を降らせそうな黒い雲が覆っている。
狭い道を幾分緊張しながら杓子沢の雪渓へと降りる。思ったほど悪い道でも無くてほっと。
遙かな山巓は杓子に鑓が天を突いているはずだが。今にも雨を降らせそうな黒い雲が覆っている。
狭い道を幾分緊張しながら杓子沢の雪渓へと降りる。思ったほど悪い道でも無くてほっと。
 天から落ちてくるような沢の流れ、周りは雲の下まで雪渓で埋まっていた。落石沢に鑓沢と見上げる雪渓山肌に目を時折やりながら抜けた。抜けた後に背後で落石音が聞こえた。
振り返れば杓子沢へ水平道をあの二人連れが歩いていた。小日向のコルから見かけなかったので途中で引き返したと思っていた。アイゼンを着けるまでもない雪渓を一旦下り鑓温泉から伸びる雪渓に出る。
天から落ちてくるような沢の流れ、周りは雲の下まで雪渓で埋まっていた。落石沢に鑓沢と見上げる雪渓山肌に目を時折やりながら抜けた。抜けた後に背後で落石音が聞こえた。
振り返れば杓子沢へ水平道をあの二人連れが歩いていた。小日向のコルから見かけなかったので途中で引き返したと思っていた。アイゼンを着けるまでもない雪渓を一旦下り鑓温泉から伸びる雪渓に出る。

ここで普通はアイゼン装着だがピッケルがあるしそのままでも行けると一休みして登り始める。小屋は見上げれば近そうだったが案内に立っている旗は何本も、間隔を見れば結構な距離。何度か息を繋いで一本一本確実に。
雪渓をようやく抜けて土の斜面もまだ登りでがあった。人声が聞こえ湯気が見えて小屋の真下に出た。 とうに着いて湯上がりにほのかに酔ってワイワイやっている連中の前を挨拶交わしてテント場へ。幾つか張ってあったがまだ余裕で。それでも下の方。テントを張れば落ち着く。まずは受け付けて一風呂と小屋へ。
とうに着いて湯上がりにほのかに酔ってワイワイやっている連中の前を挨拶交わしてテント場へ。幾つか張ってあったがまだ余裕で。それでも下の方。テントを張れば落ち着く。まずは受け付けて一風呂と小屋へ。
テント代千円は高しも温泉代5百円はまずまず。缶ビール600円も仕方なき。 テント場の上にある露天風呂は展望が利いて開放感があるが生憎曇り空。遠く頸城の山並に高妻山が望めた。
少々青っぽい澄んだ湯、湯温も丁度良し。他に一人だけでゆったり楽しんだ。湯上がりに缶ビール2缶購入してテントへ。小屋は丁度夕食中、宿泊客はまだ多くはなかった。
テント場の上にある露天風呂は展望が利いて開放感があるが生憎曇り空。遠く頸城の山並に高妻山が望めた。
少々青っぽい澄んだ湯、湯温も丁度良し。他に一人だけでゆったり楽しんだ。湯上がりに缶ビール2缶購入してテントへ。小屋は丁度夕食中、宿泊客はまだ多くはなかった。
登り始めのあの二人連れがようやく登ってきて直ぐ隣にテントを張っていた。周りのテントも夕餉中。こちらもテントに入り枝豆など煮ながら缶ビールを開ける。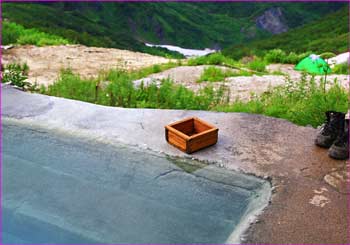 喉を鳴らす先には谷間の雪渓に戸隠から頸城の山々が雲の波と混ざり合って暮色の景。2缶は直ぐ空いてバーボンのお湯割りも少々。まだ日は長かった。
喉を鳴らす先には谷間の雪渓に戸隠から頸城の山々が雲の波と混ざり合って暮色の景。2缶は直ぐ空いてバーボンのお湯割りも少々。まだ日は長かった。
8時から9時まで女性専用となる露天風呂、夕闇迫る前にまた入れた。そうしてまた缶ビール購入し飲み直しと懲りず。
ろうそく点けるまでもなく寝袋に。
 |
 |
| (鑓温泉黄昏) | (高妻山方面展望) |
<ページ先頭へ>
7月22日[水](快晴後曇雨) 鑓温泉から白馬頂上
 久し振りの天の川はあれかと思いながらまた寝袋に、幾分冷え込んでいたが寒くはなし。暗いうちからホトトギスが鳴いていた。
薄明るくなって4時前に起き上がる。外を覗けば黎明に東空が良い色。下界は雲海に包まれ高妻山や頸城の山波は黒いシルエットでその雲海上、素敵な夜明けだった。
久し振りの天の川はあれかと思いながらまた寝袋に、幾分冷え込んでいたが寒くはなし。暗いうちからホトトギスが鳴いていた。
薄明るくなって4時前に起き上がる。外を覗けば黎明に東空が良い色。下界は雲海に包まれ高妻山や頸城の山波は黒いシルエットでその雲海上、素敵な夜明けだった。
 小屋のエンジンも動きだし、周りのテントも朝のざわつきが。お湯を沸かし味噌汁に餅入れて朝食。と、不覚にも日の出が高妻山の辺りから、カメラを取りだしかまえたときはもう遅し。
あっという間にまぶしい日が上がった。テントから小屋を見れば露天風呂に入っている人も居た。贅沢に夜明けを見ながらの温泉であったがうらやましく思うだけでテントを片付ける。
小屋のエンジンも動きだし、周りのテントも朝のざわつきが。お湯を沸かし味噌汁に餅入れて朝食。と、不覚にも日の出が高妻山の辺りから、カメラを取りだしかまえたときはもう遅し。
あっという間にまぶしい日が上がった。テントから小屋を見れば露天風呂に入っている人も居た。贅沢に夜明けを見ながらの温泉であったがうらやましく思うだけでテントを片付ける。
 早々に下って行く登山者もいた。昨日遅く着いた二人組は朝風呂入って朝食はこれからとのんびり。聞けば今日このまま下るともったいなき。でもそれも良いかと後から思えば。
朝日が小屋の背後の山々を明るく照らし、天空は澄んだ青空に願ってもない夏山と勇躍して鑓温泉を出発。賑わう小屋の前を通り登って行く。
早々に下って行く登山者もいた。昨日遅く着いた二人組は朝風呂入って朝食はこれからとのんびり。聞けば今日このまま下るともったいなき。でもそれも良いかと後から思えば。
朝日が小屋の背後の山々を明るく照らし、天空は澄んだ青空に願ってもない夏山と勇躍して鑓温泉を出発。賑わう小屋の前を通り登って行く。
 裏手を少し登れば雪渓、遙かな高みへ雪渓が伸びている。その雪渓上に先行者が一人二人。雪渓への取り付きで年配者二人がアイゼン装着中。
その一人のおばさんが先に登って行く後をこちらはアイゼン無しで。ピッケルをせっかく持ってきたのでそれを支えに。雪渓の中腹からまた山道、アイゼンはずす手間なく登って行く。
この雪渓ではガスられると直登して迷うところ、冗談におばさんに話せば、壁に突き当たりますよと冷静。そのおばさんの先へ行くことはなかった。
裏手を少し登れば雪渓、遙かな高みへ雪渓が伸びている。その雪渓上に先行者が一人二人。雪渓への取り付きで年配者二人がアイゼン装着中。
その一人のおばさんが先に登って行く後をこちらはアイゼン無しで。ピッケルをせっかく持ってきたのでそれを支えに。雪渓の中腹からまた山道、アイゼンはずす手間なく登って行く。
この雪渓ではガスられると直登して迷うところ、冗談におばさんに話せば、壁に突き当たりますよと冷静。そのおばさんの先へ行くことはなかった。
狭い道を登って行けば晴れ上がった夏空に素敵な景観が、眼下には斜面にひっつくように小屋が見え、雪渓が谷間で下っている。 雲海に高妻山などが黒いシルエットで浮かぶ。
山を見上げれば滝が天から落ちてくるような豪快さにすがすがしき。斜面の草むらにはニッコウキスゲが咲きあっているのも良し。そうしてホトトギスが鳴き、ウグイスが囀っている。
重荷がこたえる登りも我が夏山であった。
雲海に高妻山などが黒いシルエットで浮かぶ。
山を見上げれば滝が天から落ちてくるような豪快さにすがすがしき。斜面の草むらにはニッコウキスゲが咲きあっているのも良し。そうしてホトトギスが鳴き、ウグイスが囀っている。
重荷がこたえる登りも我が夏山であった。
 滝から流れ落ちてくる沢水で顔を洗ってさっぱり。左まぶたにこめかみ辺りが虫刺されに少々違和感もあったが。花を愛でながら登れば鎖場、少々気を使うも天に昇るような爽快感があった。
後ろから追い立てられるもひと息つくところで道を譲る。そうして早い下山者、単独行の若い女性。早いですねと挨拶すれば、天狗小屋に泊まったからと。その後男性も続いていた。
先程眺めた滝を左に見て上部へ抜ければ一気に鑓ヶ岳が展開した。
滝から流れ落ちてくる沢水で顔を洗ってさっぱり。左まぶたにこめかみ辺りが虫刺されに少々違和感もあったが。花を愛でながら登れば鎖場、少々気を使うも天に昇るような爽快感があった。
後ろから追い立てられるもひと息つくところで道を譲る。そうして早い下山者、単独行の若い女性。早いですねと挨拶すれば、天狗小屋に泊まったからと。その後男性も続いていた。
先程眺めた滝を左に見て上部へ抜ければ一気に鑓ヶ岳が展開した。
花畑が広がる開豁なる別天地、先に登った二人も腰を下ろして休憩中。その先にザックを降ろして花畑を愛でる。雄大な鑓の山巓、天狗ノ頭の雪渓まぶしく周りには色んな花が展開。
こちらから登って良かったと思った。 野鳥も素敵な鳴き声を聞かせてくれる。まだ人の煩さはなかった。7時にラジオで天気予報も聞いたがはっきりせず。日差しは高山でも強し。
斜面を先程のおばさんが辿っているが歩みは遅かった。休んでいた中高年の男性二人はその後をさっさと登って行く。(くびき方面展望↓)
野鳥も素敵な鳴き声を聞かせてくれる。まだ人の煩さはなかった。7時にラジオで天気予報も聞いたがはっきりせず。日差しは高山でも強し。
斜面を先程のおばさんが辿っているが歩みは遅かった。休んでいた中高年の男性二人はその後をさっさと登って行く。(くびき方面展望↓) 
大出原良きところ、顕著な雪渓が有りそれを渡ったところで荷を降ろした。雪をかじって喉を潤す。雪渓の雪をタオルに包んで首を冷やしたり帽子に入れて脳天もと涼を取る。
時折騒ぎながら降りてくる登山者も増えていた。 また急な斜面になり高山植物咲群れるのに助けられつつ。振り返れば大出原の花の台地が切れるところまで雲海が押しよせていた。
まだ頭上は蒼空に白い雲が湧く程度。稜線までまだまだだったがその斜面を上り下りする登山者を目印に登って行く。
また急な斜面になり高山植物咲群れるのに助けられつつ。振り返れば大出原の花の台地が切れるところまで雲海が押しよせていた。
まだ頭上は蒼空に白い雲が湧く程度。稜線までまだまだだったがその斜面を上り下りする登山者を目印に登って行く。
 思ったほどきつくなく人声賑やかな後立山の稜線へ。稜線へ出て展望は広がった。剣岳から日本海の景が。これから降りようかという二人組と立ち話も少々、
鑓温泉でもう一泊したいが明日は天気悪いからそのまま下ろうかなどと。虹を見たとも。山に入る前はそんな予想ではなかったのであるが雲行きは怪しくなっていた。
立ち話しただけでそのまま鑓ヶ岳へ向かう。
思ったほどきつくなく人声賑やかな後立山の稜線へ。稜線へ出て展望は広がった。剣岳から日本海の景が。これから降りようかという二人組と立ち話も少々、
鑓温泉でもう一泊したいが明日は天気悪いからそのまま下ろうかなどと。虹を見たとも。山に入る前はそんな予想ではなかったのであるが雲行きは怪しくなっていた。
立ち話しただけでそのまま鑓ヶ岳へ向かう。
さすがに夏の白馬は賑やかであった。 時折熊除け鳴り物を鳴らしながら無頓着に歩いているハイカーが気になったが。煩いですねと言えば熊がいるところを通るからなどと返される。
ただ遠ざかるのを願うだけ。鑓温泉から先を行く単独行のおばさんが白い斜面の道を登って行く。その遙かな山巓が鑓ヶ岳、白雲が湧いて青空に山肌が良きコントラスト。山の端に人が蟻のように群れている。
時折熊除け鳴り物を鳴らしながら無頓着に歩いているハイカーが気になったが。煩いですねと言えば熊がいるところを通るからなどと返される。
ただ遠ざかるのを願うだけ。鑓温泉から先を行く単独行のおばさんが白い斜面の道を登って行く。その遙かな山巓が鑓ヶ岳、白雲が湧いて青空に山肌が良きコントラスト。山の端に人が蟻のように群れている。
 そろそろ昼と道からはずれた稜線尾根の高台にザックを置いた。下ってくるハイカーが時折、目が合えば挨拶交わす程度。展望は左右に、剣岳が幾分変わった位置から尖って見ゆ。
あの想い深し毛無三山が残雪の筋幾つか緑濃く存在感ある山巓であった。その遠く能登半島が伸びて富山湾も望見出来る。鑓ヶ岳は白い山巓、空をしきって。右手には今朝登って来た鑓温泉の谷である。
こちらは豊かな雪渓がまぶしく遙かな山峡。遠く頸城の山々に高妻山などが雲のまにまに見えている。先程登ってきた稜線を見下ろす先には天狗小屋が懐かしき。あそこで幕営した時は台風に遭遇だった。
春先の八方尾根は夏姿、その先の鹿島槍なども残雪の筋いくつかある程度。まだ展望は利いていた。
そろそろ昼と道からはずれた稜線尾根の高台にザックを置いた。下ってくるハイカーが時折、目が合えば挨拶交わす程度。展望は左右に、剣岳が幾分変わった位置から尖って見ゆ。
あの想い深し毛無三山が残雪の筋幾つか緑濃く存在感ある山巓であった。その遠く能登半島が伸びて富山湾も望見出来る。鑓ヶ岳は白い山巓、空をしきって。右手には今朝登って来た鑓温泉の谷である。
こちらは豊かな雪渓がまぶしく遙かな山峡。遠く頸城の山々に高妻山などが雲のまにまに見えている。先程登ってきた稜線を見下ろす先には天狗小屋が懐かしき。あそこで幕営した時は台風に遭遇だった。
春先の八方尾根は夏姿、その先の鹿島槍なども残雪の筋いくつかある程度。まだ展望は利いていた。
 |
 |
| (天狗小屋に鹿島槍ヶ岳) | (剣岳望む) |
せっかく持って来た缶ビールを冷やすべき雪渓はなかったのでしばらく風で、日が雲間に入れば吹き抜ける風は寒かった。靴下まで脱いでシートに座ったが汗を拭いて直ぐ履き直す。ヤッケも着た。
冷えるはずもないが缶ビールは意外と飲めた。喉を鳴らすまではいかなくも甘みが出てまた変わったドライであった。お湯を沸かす事はなくちょいとしたつまみにパンで軽い昼と。
また重い荷を担いであの鑓ヶ岳へと向かう。見た目よりきつくはなく淡々と足を運んでいけば山頂の左乗越へ。山頂から直接下ってくる稜線コースは団体さんが連なっていた。
一旦西から雲が広がったがまた山が見えるようになり剣岳の鋭鋒に毛勝三山もまたはっきり望めるようになった。(20年前にあの左端の雪渓へ迷い下ったのだった。↓)

そうして前方に杓子岳が見えその先には白馬岳が雄大に峰を高めていた。
非対称山稜はっきり、左側は穏やか、日本有数のお花畑が展開するが右側はそのまま奈落に落っこちる懸崖である。 まだ雲にからまれることなく待望の勇姿であった。
残雪豊富な旭岳から清水尾根も気をひく景観であった。あの尾根を辿って奥深き黒部峡谷にと誘われるが明日考えよう。
まだ雲にからまれることなく待望の勇姿であった。
残雪豊富な旭岳から清水尾根も気をひく景観であった。あの尾根を辿って奥深き黒部峡谷にと誘われるが明日考えよう。
ザックを置いて頂上往復。頂上には数人がたむろしていたが山頂標識やら三角点を確認し一廻り展望して引き返す。 鑓温泉側はとうに雲に覆われていた。戻って白馬へと下って行く。
こちら側は花畑が豊富だった。色んな花が、ウルップソウ、ミヤマオダマキやら等々。今度は西側から本格的に黒雲が押しよせていた。前方の白馬岳も雲に隠れてしまった。(旭岳望む↓)
鑓温泉側はとうに雲に覆われていた。戻って白馬へと下って行く。
こちら側は花畑が豊富だった。色んな花が、ウルップソウ、ミヤマオダマキやら等々。今度は西側から本格的に黒雲が押しよせていた。前方の白馬岳も雲に隠れてしまった。(旭岳望む↓) 
花を愛でながら杓子沢のコルへ。そこから騒ぎながら登ってくる若者一団と遭遇。そう気にならずも雷鳥の鳴き声がしたので、挨拶がてら随分声が大きいですね、雷鳥もびっくりしているよと。
右手の斜面のお花畑にいる親鳥を見ながら。 リーダー格のような女性がのぞき込んでまた騒ぐ。シーっと注意。男性群もカメラなどかまえながら、いるいると子供が4羽、いや5羽などと。
実際は6羽連れていた。母鳥はクークーと鳴きながら見守っている。若者達はしばらく見ていたが先行していた仲間に呼ばれて鑓ヶ岳へ去って行った。軽荷だったので白馬から往復か。 (雷鳥親子→)
リーダー格のような女性がのぞき込んでまた騒ぐ。シーっと注意。男性群もカメラなどかまえながら、いるいると子供が4羽、いや5羽などと。
実際は6羽連れていた。母鳥はクークーと鳴きながら見守っている。若者達はしばらく見ていたが先行していた仲間に呼ばれて鑓ヶ岳へ去って行った。軽荷だったので白馬から往復か。 (雷鳥親子→)
 鑓温泉からの年配の男性もいて二人でしばらく雷鳥親子の行動を見ていた。こちらが写真を撮るのが分かっているかのように岩場でポーズもとってくれた。登山道の近くの花畑まで寄って来たりと。
時々行き交うハイカーにも教えながらだった。戻るように斜面の反対側へ消えるまで20分ほど楽しんだ。気がつけばガスに覆われていた。(←ガスる杓子岳)
鑓温泉からの年配の男性もいて二人でしばらく雷鳥親子の行動を見ていた。こちらが写真を撮るのが分かっているかのように岩場でポーズもとってくれた。登山道の近くの花畑まで寄って来たりと。
時々行き交うハイカーにも教えながらだった。戻るように斜面の反対側へ消えるまで20分ほど楽しんだ。気がつけばガスに覆われていた。(←ガスる杓子岳)
コルへ下れば後から来た二人連れに声をかけられた。何となく見覚えが、鑓温泉でテントを張っていた二人だった。二人は今夜はテントを止して小屋に泊まるような話を、予報で天気が荒れるからと。 風が強いと往生するテント場に納得。二人は急ぐように歩いたり急に立ち止まったりとしゃべりながらゆっくりしていた。
 ガスってしまった杓子岳ではないがトラバース道と決めて。黒部峡谷側の斜面が見えるだけ、花畑も終わりハイマツの尾根道。山側にはコマクサも時折あった。そうしてまた鳴き声が、
右手上のハイマツに親鳥が見えた。先程の二人も追いついてきて教えて上げる。子の存在が見えるほど近くはなかった。空は益々暗く雲に覆われていく。辿る先の稜線も見えなくなってしまった。
杓子への分岐を過ぎてまだまだ遠し。
ガスってしまった杓子岳ではないがトラバース道と決めて。黒部峡谷側の斜面が見えるだけ、花畑も終わりハイマツの尾根道。山側にはコマクサも時折あった。そうしてまた鳴き声が、
右手上のハイマツに親鳥が見えた。先程の二人も追いついてきて教えて上げる。子の存在が見えるほど近くはなかった。空は益々暗く雲に覆われていく。辿る先の稜線も見えなくなってしまった。
杓子への分岐を過ぎてまだまだ遠し。
最低鞍部へ出た頃ポツポツきていた雨が本降りになってしまった。岩影でカッパを取りだし着用。ザックカバーも着け、カメラはしまった。雨に煙った稜線を登って行く。 右手の斜面にクルマユリやらシナノキンバイなどお花畑が広がるも写真に撮れずや残念。見覚えのある岩頭やら岩場に頂上宿舎が近いことが分かるもまだ一登りあった。後ろについていた二人連れの姿は見えず。
右手の斜面にクルマユリやらシナノキンバイなどお花畑が広がるも写真に撮れずや残念。見覚えのある岩頭やら岩場に頂上宿舎が近いことが分かるもまだ一登りあった。後ろについていた二人連れの姿は見えず。
 丸山の展望台も生憎だったが雨は止んでいた。ガスが晴れて旭岳が見えればもうすぐ。稜線に人影や声が聞こえれば頂上宿舎の幕営地が右手下に見えてきた。何度か幕営したところ、
勝手は知っていた。花畑に色んな花が咲き群れていたが生憎天気が悪し。分岐を下ってテント場へ。高校の山岳部が真ん前を数張り陣取っていた。ワイワイ騒いでいたがまだ夕食には早かった。
その間を抜けて前と同じ小屋側の斜面の下に張る。風はあったがそう気になるほどでもなくほっとした。
丸山の展望台も生憎だったが雨は止んでいた。ガスが晴れて旭岳が見えればもうすぐ。稜線に人影や声が聞こえれば頂上宿舎の幕営地が右手下に見えてきた。何度か幕営したところ、
勝手は知っていた。花畑に色んな花が咲き群れていたが生憎天気が悪し。分岐を下ってテント場へ。高校の山岳部が真ん前を数張り陣取っていた。ワイワイ騒いでいたがまだ夕食には早かった。
その間を抜けて前と同じ小屋側の斜面の下に張る。風はあったがそう気になるほどでもなくほっとした。
着替えを済まし今宵は少々厚着でと。山荘に缶ビール仕入れには大回り、トイレの直ぐ先に裏口が見えているがロープで出入り禁ずと。食事しても良かったが中途半端にテントでが落ち着くと。
受け付けは17時からと紙が貼ってあった。先程の二人はテント場に見えずやはりどちらかの山荘に宿ったようだ。枝豆をまた茹で肴にビールを飲む。テントからは直ぐ斜面に花畑が見えていた。
ロング缶を飲み、レギュラー缶を空ける頃には空が明るくなった。 青空ものぞいて期待が膨らんだがそれっきり。
青空ものぞいて期待が膨らんだがそれっきり。
17時前に受け付けの案内があったがしばらくしてトイレと同じ建屋の受け付け所へ。やはり千円だった。高校生らも同じですかと聞けば変わりありませんとつっけんどん。 その後受付も確認が済んだのか直ぐ閉められてしまった。もう飲み物類を購入することはなかったが。山岳部の連中も夕食の騒ぎは済んでいた。夕暮れはまた霧に包まれその内雨になっていた。 風も出て本降り、明日が気になる風雨と。酔いに任せてまた明かり点けることなく寝てしまった。 <先頭へ>
7月23日[木](雨後曇) 白馬大雪渓下山、帰京
 昨夜から降り続いた雨は一旦止んで風も幾分治まって助かった。起き上がったのは5時過ぎ、朝食はパンで。風が時折テントを揺らすので昔の失敗を繰り返さないとガスは使わず。
停滞も考えていたが一旦止んだので出発とテントの中でパッキング。雨がまた降りだしたがなんとかテントを撤収出来た。
昨夜から降り続いた雨は一旦止んで風も幾分治まって助かった。起き上がったのは5時過ぎ、朝食はパンで。風が時折テントを揺らすので昔の失敗を繰り返さないとガスは使わず。
停滞も考えていたが一旦止んだので出発とテントの中でパッキング。雨がまた降りだしたがなんとかテントを撤収出来た。
3時頃から騒いでいた高校山岳部連中は雨の中にそのまままだ、出発するような気配なし。雨宿りはトイレだけであった。その入口のスペースでパッキングをやり直す。単独行の男性が入ってきて、 今日中に下山しなければならないが雪渓下るより白馬大池へと迷いながらも向かって行った。雨はまた本降りになっていたので大雪渓の下りは危ないかと同じく白馬大池から蓮華温泉へと向かうつもりで雨の中を出る。
 頂上宿舎の分岐まで行ってもまだ迷ったが白馬山荘から降りて来た女性3人組が大雪渓へ下って行くので決心してその後を。雨は本降り、視界も4~50㍍先は雨に煙っていた。
少々下ると花畑が展開したがカメラはしまったままただ愛でるだけとなった。小沢なのか雨のせいなのか水水の中を辿るよう。2533㍍地点の看板があるところではコンパクトデジカメG15を取りだし数枚撮った。
右手に顕著な雪渓が展開していたが雨の中に判然とせず。ミソサザイの囀りもむなしく響くだけ。
頂上宿舎の分岐まで行ってもまだ迷ったが白馬山荘から降りて来た女性3人組が大雪渓へ下って行くので決心してその後を。雨は本降り、視界も4~50㍍先は雨に煙っていた。
少々下ると花畑が展開したがカメラはしまったままただ愛でるだけとなった。小沢なのか雨のせいなのか水水の中を辿るよう。2533㍍地点の看板があるところではコンパクトデジカメG15を取りだし数枚撮った。
右手に顕著な雪渓が展開していたが雨の中に判然とせず。ミソサザイの囀りもむなしく響くだけ。
 後ろから何人かが付いてきていた。また雪渓に出合ったがアイゼンはつけずそのまま。後ろから着いてきていた年配の二人連れは奥さんに促されて装着していた。でも直ぐ途切れて小沢のような道を下る。
避難小屋があったが中に入る気分にもならずG15を取りだし数枚撮る。ここからも小雪渓まで水道。
後ろから何人かが付いてきていた。また雪渓に出合ったがアイゼンはつけずそのまま。後ろから着いてきていた年配の二人連れは奥さんに促されて装着していた。でも直ぐ途切れて小沢のような道を下る。
避難小屋があったが中に入る気分にもならずG15を取りだし数枚撮る。ここからも小雪渓まで水道。 雪渓の横断も特にアイゼン付けるまでもなく。ねぶか平の花畑もクルマユリやらハクサンイチゲなど咲群れていたが残念、
雨は降り止むことはなかった。右手の杓子の荒れた岩肌も煙っているので落石跡が見えるだけ。滝のように落ちる沢は雪渓の下に不気味流れ落ちていた。クレパスも気になる光景だった。
雪渓の横断も特にアイゼン付けるまでもなく。ねぶか平の花畑もクルマユリやらハクサンイチゲなど咲群れていたが残念、
雨は降り止むことはなかった。右手の杓子の荒れた岩肌も煙っているので落石跡が見えるだけ。滝のように落ちる沢は雪渓の下に不気味流れ落ちていた。クレパスも気になる光景だった。
白馬大雪渓の上部に下って一休み。二人の女性がこの雨の中を登ってきた。かすかに見える雪渓上にも人影が幾つか。よくこんな雨の中を登ってくるものだと。単独行の男性も雪渓から上がってきたところ。 アイゼンはいらないだろうと雪渓上に降り立ちピッケル片手でそのまま下って行く。
アイゼンはいらないだろうと雪渓上に降り立ちピッケル片手でそのまま下って行く。
雨に煙る大雪渓の至る所に岩石が散らばり落ちていた。運を天に任せてその一筋ある雪渓の道を下ったが2~3回滑って転んだ。ピッケルがあるから重いザックでも立ち上がれたが厳しかった。
振り向けば年配の二人連れだけが迫ってきていた。追いついてこられて片言挨拶、二人はアイゼン装着で年配ながらも足取り確かに下って行く。こちとらは斜め歩きで慎重に下るので遅し。 登ってくる登山者には危なっかしく見られたようであるがそれでもアイゼン取りだして装着する気までならなかった。(←大雪渓上部で)
登ってくる登山者には危なっかしく見られたようであるがそれでもアイゼン取りだして装着する気までならなかった。(←大雪渓上部で)
幸いにも落石は起きなかった。擦れ違った登山者が下で聞いた話をまた聞きで散らばっている落石は昨日はなかったとか。夜間に落ちたようだ。
 所々落石注意の看板がおいてあったが雨に煙る杓子岳の山肌を見ても注意しようがなかった。雨は益々降り出し、雪渓も下に行くほど堅く凍てついていた。
晴れていれば登ってくる登山者のアイゼンなどでやわらかくなり足場がしっかりするのであるが。ただ滑って転んだときに苦労するので一歩一歩慎重。完全に凍結したところではさけて下る。
目に付いていた大きな落石を過ぎれば安心と目安に。(白馬大雪渓も生憎雨の中→)
所々落石注意の看板がおいてあったが雨に煙る杓子岳の山肌を見ても注意しようがなかった。雨は益々降り出し、雪渓も下に行くほど堅く凍てついていた。
晴れていれば登ってくる登山者のアイゼンなどでやわらかくなり足場がしっかりするのであるが。ただ滑って転んだときに苦労するので一歩一歩慎重。完全に凍結したところではさけて下る。
目に付いていた大きな落石を過ぎれば安心と目安に。(白馬大雪渓も生憎雨の中→)
落石帯を過ぎて幾分安心も、先を下る年配二人からはどんどん離されて行く。登ってくる登山者達は皆さんしっかりアイゼン装着。その中の年配者が見かねてピッケルで滑って行けばと嫌みも言われた。
それでもそのまま後半は転ぶことなく突端に下り着いた。二人にも追いついた。彼等がアイゼンはずす間に先へ下る。 道は沢のようになりズバズバ水をけって下る。左手の口が開いた雪渓に見える水流は凄まじいかった。
道は沢のようになりズバズバ水をけって下る。左手の口が開いた雪渓に見える水流は凄まじいかった。
(←大雪渓下流)
先を行く人影が見えていたが早足で追いつけず。道は沢のようになっていたがとうとうその流れに足が止まった。右手の沢から本流に流れ下る沢がせき止められたのか大岩を乗り越えて滝のように道をふさいでいた。 先に行った人影はどう乗り越えたか見ることが出来なかったのでしばらく思案。滝の下をずぶ濡れでくぐり抜けるか、落ちた先の流れに木道のようなのが有りそこを一気に渡るかと。 そこへ上から先程の年配の二人がやって来た。男性が余り躊躇することなく滝が落ちて流れゆく先の木道を渡った。その後を連れ合いに指示しながらポールに手を添えるように引き上げた。 旦那がこちらにも手を貸そうとしたが手でさえぎってそのまま同じように渡った。見た目ほど悪くはなかったが我が左目の不自由さでは判断が出来なかったのである。雪渓であった連中は皆さんここを通ったのだ。 気の弱い人はここで引き返しただろう。転べば本流に飲み込まれそれこそ遭難であった。
 その先に白馬尻の小屋があったが皆さん軒先に雨宿り中。中に入って寛ぐにはまだ1時間歩かねばならないので止した。G15で雪渓と小屋を写しただけでまた下り始める。
幾分広くなり歩きやすくなった道だったがまだ沢道のような所もあった。登ってくる人もまだいたが白馬尻までは問題はなかった。でもこれ以上の大雨が降るようだとこの白馬尻までも困難となるようであった。
その先に白馬尻の小屋があったが皆さん軒先に雨宿り中。中に入って寛ぐにはまだ1時間歩かねばならないので止した。G15で雪渓と小屋を写しただけでまた下り始める。
幾分広くなり歩きやすくなった道だったがまだ沢道のような所もあった。登ってくる人もまだいたが白馬尻までは問題はなかった。でもこれ以上の大雨が降るようだとこの白馬尻までも困難となるようであった。
林道に出て幾分明るくなったように尾根が見えてきた。車が2台行き止まりに駐車してあった。その先で道を横切る沢の流れはトラックは通れても乗用車は流されそうな勢いであった。 右手に木橋があったので登山者は大丈夫。雨の林道歩きも慣れていたがカッパを着ていても汗と混ざって濡れて気持ち悪し。
ようように登り始めの鑓温泉登山口に出合い、その先のブナ林を右に下れば猿倉山荘が見えてほっとした。山荘の売店前のトタン屋根下で落ち着く。カッパを脱ぎ上だけ着替えてすっきり。 まだ空いていたので生ビールに枝豆つまみ、カレーライスでしばしのんびり。でも直ぐ登山者で賑やかに、鑓温泉から下山も同じ頃だった。車の人はそのまま駐車場へ向かうがタクシーやバスの人はここで。 若い山ガール組に若者もいて賑やか。こちらは生ビールの後はロング缶追加とそのざわめきを見ながら打ち上げ。
下りに一緒だった年配夫婦も下って来て傍に。それで話しをして高知から来たとか、昨日は白馬大池からなどと聞く。車は八方に置いてあると。とうに隠居の二人か、奥さんの目はしっかりしていた。 四国の山にも何度かと話しをして打ち解けた。それで八方までタクシーという話になったが、もうタクシーは出払っていた。
 1時間余りも直ぐ、まだ雨は止んでいなかったがバス発着所へ一緒に。バスは数人だけ乗せて上ってきた。乗る人もまだ少なかったが発車する頃には結構な。ザックも濡れたまま若い二人の女性も乗り込んできたがさわやか、
うなじがまぶしい若さだった。最後部の席に座って山を後にする。八方の駐車場で幾人か降り、バスセンターでは高知夫婦や若い山ガールたちも降りて静かになった。
バスの去り際に窓を開ければ気がついて高知夫婦が笑顔で見送ってくれた。今宵は八方山荘に宿泊と言っていたが天気が回復することを願って。
1時間余りも直ぐ、まだ雨は止んでいなかったがバス発着所へ一緒に。バスは数人だけ乗せて上ってきた。乗る人もまだ少なかったが発車する頃には結構な。ザックも濡れたまま若い二人の女性も乗り込んできたがさわやか、
うなじがまぶしい若さだった。最後部の席に座って山を後にする。八方の駐車場で幾人か降り、バスセンターでは高知夫婦や若い山ガールたちも降りて静かになった。
バスの去り際に窓を開ければ気がついて高知夫婦が笑顔で見送ってくれた。今宵は八方山荘に宿泊と言っていたが天気が回復することを願って。
白馬駅に着いた頃は雨も小降りになっていた。やはり大糸線の電車はしばらくなかった。案内所に温泉を聞いたが気分が乗るところはなく駅隣の足湯で済ませる。着替えは駅のトイレで。 左目こめかみ辺りが虫にやられて気になっていたが鏡を見て腫れぼったくなっていたのにはびっくり。やはりサングラスはかけたまま。右親指は転んだときの打撲が、両足のすねには傷もとそう無事でもなかった今回の旅であった。 すっきりしたので帰藤することに決めて13時50分の長野行き特急バスに。白馬駅で長野からの新幹線も購入。ビールは新幹線でと我慢。
 バスを待っていると係員がやって来て切符の購入やらザックもと世話してくれた。八方からやって来た特急バスは空いていた。多分山で合った人も居るだろうが知らず。 途中で寝込んで気が付いた時はもう長野に入っていた。
順調で15時前に東口到着、曇り空だった。15時10分のアサマに間に合ったが買い換えるのも面倒と購入していたはくたか号にそのまま。時間つぶしに駅周りぶらり。待合所のテレビで大相撲中継中、
信州木曽期待の御嶽海が映し出されて初めて拝見。成績は十両優勝する勢い、まだザンバラ髪、学生出身だった。(晴れ上がった車窓↓)
バスを待っていると係員がやって来て切符の購入やらザックもと世話してくれた。八方からやって来た特急バスは空いていた。多分山で合った人も居るだろうが知らず。 途中で寝込んで気が付いた時はもう長野に入っていた。
順調で15時前に東口到着、曇り空だった。15時10分のアサマに間に合ったが買い換えるのも面倒と購入していたはくたか号にそのまま。時間つぶしに駅周りぶらり。待合所のテレビで大相撲中継中、
信州木曽期待の御嶽海が映し出されて初めて拝見。成績は十両優勝する勢い、まだザンバラ髪、学生出身だった。(晴れ上がった車窓↓)
はくたかは少々早めにホームに、空いていたが指定の席へ。缶ビール飲みながら雨が上がった長野の山村風景見ながら。山はまだ雲の中も明るい田園。ゆったりだったが軽井沢で込んで来て隣も埋まった。
高崎過ぎれば早し、関東は晴れて遠く富士も見えていた。大宮過ぎてそろそろ降りる準備と登山靴に履き替える。上野で乗換はもう何度も、上野東京ラインのホームへ。上野からは座れて助かる。東京駅で込んで来て満席、
後は会社帰りに混みあう車内。藤沢には18時過ぎ帰着。
<先頭へ> (平成27年7月30日完)